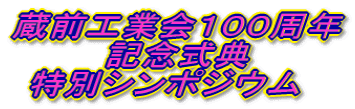TOP
上へ戻る
蔵前工業会(東京工業大学同窓会)が100周年を迎えた。
同窓会誌で、ノーベル賞受賞者による特別シンポジウムの
開催を知り、それに先だって記念式典・懇親会があるという
ので、高輪プリンスホテルまででかけた。
懇親会の最後は、学歌を歌う。
男性合唱団のシュワルベンコールの
方々による合唱と廣池さんの伴奏。
三好達治の詩は重厚だ。
記念式典は同窓会理事長古川正彦さんの挨拶から
始まった。そして、式典には来賓がいる。経済産業副大臣の
松あきらさんの祝辞が続く。芸能界から転身した松さんは
男だらけの出席者のなか華やいだ雰囲気を醸し出した。
しかも、的を射た挨拶にはびっくりした。議員さんは違う!
続いて学長の祝辞。同窓会と大学との関係の大切さを
感じた。また、続いて行われた手島工業教育財団の遠藤さん
の記念講演会。東京職工学校から始まった東京工業大学の
歴史。その中で大学への昇格の際に同窓会の活動がどれだけ
強いものであったか。そして、初代蔵前工業会会長の手島精一
さんについてのお話しがあった。歴史の重みを感じた。
きたさん紀行
OBには、多才な方が多いが物理学者でありながら、ジャズピアニスト
という方もいらっしゃる。しかも女性。廣池英子さんだ。
懇親会のゲストとして、演奏をして下さった。物理学者だけに
メタステイブルとか量子論的な考え方で曲が作られているのも面白い。
つい、CDと楽譜を買ってしまった。ミーハーである。
記念式典のあとには懇親パーティーが行われた。記念式典の
来賓である松あきらさんや特別シンポジウムのパネラーでもある
白川英樹さんも顔を出してくださった。
会場は満員。ただ、先輩ばかり。まだまだ若造だなと思う。
皆さん元気だ!
日立の社長さんである庄山さんも駆けつけた。
午後からは、一般の方々も対象にした特別シンポジウムが飛天の間
で行われた。芸能人が披露宴をするところだ。東都大学野球連盟の
記念式典もここで行われた。2000人以上の人たちが集まった。
入り口には、協賛企業の名前がずらり。すごい!
まずは学長の挨拶から始まった。記念式典の時とは違う雰囲気。
八王子支部の講演会に来て頂いた時を思い出す。
「21世紀の科学技術のフロントランナーとしてのあるべき姿」
と題したシンポジウム。どんな話が聞けるのだろうか?
来賓挨拶は、与謝野馨金融担当大臣。大物だ!
そして、特別シンポジウムが始まった。白川英樹さん、野依良治さん、
小柴昌俊さんのノーベル賞受賞者と元学長の末松安晴さん、そして
進行役はNHKの平石富男さん。そうそうたるメンバーだ。
科学離れが叫ばれるなか、文部科学省は第3次科学技術基本計画
を推進しようとしている。研究者の自由な発想による研究と政策としての
研究の2つの柱がある。近頃の風潮では、結果が出ない研究はだめ!
という感じだが、実は基礎的な研究が大切なのだ。何の役に立つかで
はなく、ものの本質を極めることの重要性をパネラーの先生方も
強調していた。
先生方と科学の出会いはそれぞれだ。白川先生は自然の中での体験が
あとになって科学との出会いにつながる。野依先生は家には学術書が
たくさん。湯川秀樹先生のノーベル賞受賞大きな転機となった。小柴先生は
朝永振一郎先生との出会い。飲んでばかりだったそうだが。末松先生は
学校で教えないことで楽しいことがたくさんあると気づいた時だそうだ。
これからの若い世代の育成については、小柴先生は科学を好きな先生に
小学校高学年から中学生で出会うことだとおっしゃった。自分が好きだと
思っている先生に習うことができれば好きになる子も多くなるだろう。
白川先生は、自分で実際にやることの大切さを強調された。いくらビデオ
など視聴覚教材が発達しても、自分で体験したことにはかなわない。
できるだけ触れて欲しい。とおっしゃった。
野依先生は、科学が効率主義になじまないものであることを社会に
理解してもらう活動をしていくことが大切だと強調された。
約3時間のシンポジウムは
さすがに疲れたが、4人の先生
方の情熱を感じることができた
ことが良かった。
それぞれの先生方の人柄も
面白かった。白川先生はひょう
ひょうとしてマイペース。
野依先生はバイタリティー
あふれる感じ。
小柴先生は、いいおじいちゃん。
話しが一番面白かった。
末松先生は、研究者としての顔と
2つの大学で学長を務めた経営的な
見方をされる。
シンポジウムの最後は、質疑応答。若い大学生の研究者や工業高校生が
質問した。慶應や東大の優秀な学生さんの悩みにバシッと答えていた。
「人のやったことについていると不安。自分ではじめればいい。」
「いろいろなことを体験して自分の本当にやりたいことがみつかればいい。」
という言葉が印象的だった。野依先生は、「20世紀は競争の時代だった。
21世紀は協調の時代にしていかなくてはいけない。そして、文化を理解し
受け入れられる科学でなければこれからの時代はたちいかなくなってくる。」
と強調されていたのが印象的だった。
貴重な講演会に参加できて良かった。生徒たちにどう教えていったら
いいのか。理科教育における原点を再認識することができた。
なお、このシンポジウムの模様は4/8(土)午後11時半より
NHK教育テレビで放映されます。
興味のある方はぜひご覧下さい!